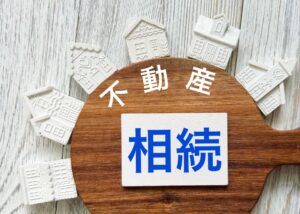配偶者居住権とは?自宅を守るための相続対策を解説
こんにちは。世田谷・渋谷・目黒・三軒茶屋相続相談センターの相続診断士の乾です。
相続の場面で、多くのご家庭が直面するのが「配偶者が安心して住み続けられるか」という問題です。 特に、世田谷や目黒や渋谷といった不動産価値の高い地域では、自宅をどう相続するかが家族にとって大きなテーマとなります。
本記事では、2020年4月に施行された新しい制度「配偶者居住権」について、わかりやすく解説いたします。 配偶者が自宅に安心して住み続けられるようにするための具体的な方法と、注意すべきポイントを丁寧にご紹介します。
第1章|配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、相続後も無償で自宅に住み続けられる権利のことです。
これまで、配偶者が住み続けるためには、不動産そのものを相続するか、家賃を払って住み続けるしかありませんでした。 しかし、配偶者居住権を使えば、所有権を持たずに居住権だけを取得できるため、財産全体のバランスを取りながら住まいを守ることができます。
1-1. 制度創設の背景
日本では高齢化が進み、配偶者の生活保障が大きな課題となっていました。 配偶者居住権の導入により、次のようなメリットが期待されています。
- 配偶者が安心して住み続けられる
- 他の相続人との財産分割がしやすくなる
- 相続争い(争続)の防止につながる
第2章|配偶者居住権の特徴
2-1. 配偶者が亡くなるまで有効
配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで続きます。 つまり、住まいに困ることなく、老後を安心して過ごすことができます。
2-2. 所有権と分離できる
自宅の所有権と居住権を分けることができるため、所有権は子供たちに、居住権は配偶者に、という形で分配できます。
2-3. 財産評価が低くなる
配偶者居住権は通常の所有権より評価額が低いため、配偶者の法定相続分を超えずに済み、税務上もメリットがあります。
第3章|配偶者居住権の活用例
ケース1|夫亡き後、妻が自宅に住み続ける
【背景】 夫(80代)が亡くなり、相続人は妻と子供2人。 財産は自宅(土地・建物評価額:1億円)と預金2,000万円。
【問題点】
- 妻が自宅を相続すると、子供たちへの現金分配が難しい
- 自宅を売却せずに妻が住み続けたい
【配偶者居住権活用】
- 妻に配偶者居住権を設定(評価額3,000万円程度)
- 自宅の所有権は子供たちに相続
- 預金2,000万円は子供たちに分配
➡ 妻は安心して住み続けられ、子供たちも公平に財産を受け取ることができました。
第4章|配偶者居住権を利用するための条件
- 被相続人が所有していた建物に居住していたこと
- 配偶者居住権を相続開始後に設定すること(遺産分割協議や遺言書で定める)
- 建物の保存・修繕費用は基本的に配偶者負担
第5章|注意点とデメリット
5-1. 将来売却しにくくなる
居住権が設定された不動産は、自由に売却しづらくなります。 子供たちが将来的に売却を希望しても、配偶者の同意が必要です。
5-2. 住まいの維持費は配偶者負担
建物の維持管理費や固定資産税は、基本的に居住権を持つ配偶者が負担する必要があります。
5-3. 財産分割協議でトラブルになる可能性
配偶者居住権を設定するかどうかは、他の相続人との話し合いが必要です。 合意が得られないと、制度を活用できない場合もあります。
第6章|配偶者居住権を活用するためのポイント
6-1. 遺言書の作成をおすすめ
遺言書で配偶者居住権の設定を明記しておけば、相続発生後のトラブルを防ぐことができます。
6-2. 専門家に相談する
相続や不動産の専門家に相談しながら進めることで、最適な対策を取ることができます。 特に税金や不動産の評価に関わる部分は、プロのアドバイスが重要です。
第7章|まとめ
✔ 配偶者居住権は、配偶者が安心して住み続けるための新しい権利 ✔ 自宅の所有権と居住権を分けることで、柔軟な相続が可能に ✔ デメリットもあるため、事前の計画と家族の話し合いが大切
相続対策は、「元気なうちに始める」ことが最大のポイントです。
「自宅を守りたいけど、どうすればいいかわからない」 「配偶者居住権を使うべきか相談したい」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
世田谷・渋谷・目黒・三軒茶屋相続相談センターでは、専門家があなたの相続対策を丁寧にサポートいたします。
✅ 初回相談無料 ✅ 土日・平日夜も対応可能 ✅ 女性スタッフ在籍で安心
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【監修】世田谷・渋谷・目黒・三軒茶屋相続相談センター
【掲載カテゴリ】相続の基礎知識
【本記事のキーワード】 配偶者居住権 相続 自宅保護 生前対策 世田谷 渋谷 目黒 相続相談