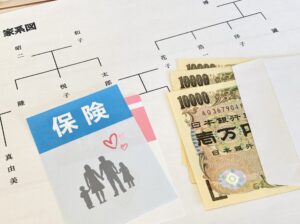遺産分割の「持ち戻し免除」とは?生前贈与の落とし穴に注意
こんにちは。世田谷・三軒茶屋相続相談センター相続診断士の乾です。
今回は、「持ち戻し免除とは何か」をテーマに、生前贈与に関する落とし穴を含めて詳しく解説いたします。ご自身でも使える知識を得て、「損をしない相続対策」ができるような記事にしました。
遺産分割の「持ち戻し免除」とは?生前贈与の落とし穴に注意
リード(導入)
ご親御さん(80代)が世田谷区に自宅を持ち、都内に不動産や金融資産をいくつかお持ちのご家族—。
相続が発生した際、配偶者とお子さん2人(あなたを含む)で分けることになりますが、生前に贈与をされたものがあると、その分を「考慮」する必要があります。特に「持ち戻し」の制度が関わると、思わぬ税負担や遺産分割トラブルが起こることがあります。
その一方で、「持ち戻し免除」条項を贈与契約や遺言で予め設けておくことで、生前贈与された財産を遺産分割の対象外にすることができます。これが「持ち戻し免除」の制度です。
本記事では、持ち戻しと持ち戻し免除とは何か、そのメリット・デメリット、生前贈与に関する注意点、事例を通じてどのように対策ができるかを整理します。制度を正しく理解して、将来の相続で「損をしない選択」ができるようにしていきましょう。
第1章|持ち戻しとは何か?
まず「持ち戻し」とは何かを確認しましょう。
- 生前贈与:被相続人が生前に相続人に対して財産を贈与すること。
- 相続開始後の遺産分割では、生前贈与した分を「遺産に戻して」考えることがあります。これが「持ち戻す」こと。
法律的根拠
民法で定められており、生前贈与された財産が遺産分割の際に公平性を保つために遺産に持ち戻されることが原則としてあります。ご親御さんが子に土地をあげた、あるいは多めの贈与をしたとき、それを後で「遺産分割で考慮する」ということです。
第2章|持ち戻し免除とはどういう制度か?
「持ち戻し免除」とは、将来の遺産分割の際に、生前贈与した財産を遺産に持ち戻さなくても良い、という取り決めのことです。
どのように設けるのか
- 贈与契約書に「持ち戻しを免除する」という条項を入れる
- 遺言書に「この贈与については持ち戻さない」という指示を入れる
このような条項があれば、生前贈与したものが遺産分割で考慮されず、「事前に渡したものは渡したまま」とできるのです。
第3章|持ち戻し免除のメリット・デメリット
制度を採用する前に、良い点と注意点を整理しておきます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 贈与された財産を遺産分割に戻さなくてよいので、生前贈与された方々も「渡した分はそのまま」受け取れる安心感がある。 | 他の相続人が「不公平だ」と感じる可能性があり、家族間で揉める原因になることもある。 |
| 遺産分割協議がシンプルになる。 | 遺留分請求の対象になる場合、「持ち戻し免除」の条項でも完全に免除できないケースがある。 |
| 贈与した財産を使った方も安心。たとえば、お孫さんの教育資金やお子様の住宅資金などを生前に渡しておきたい場面で有効。 | 制度をきちんと文書化しないと認められないことがある(口約束では無効になる可能性がある)。 |
第4章|「持ち戻し免除」を使うべきケース・使わないほうがよいケース
制度を使うかどうかは、家族構成や財産内容、将来の見通しによって異なります。
使うべきケース
- 財産が不動産中心で現金が少ない家庭。贈与しておかないといざというとき納税資金や分割資産が足りなくなる可能性がある。
- お子さんやお孫さんなど複数の相続人にあらかじめ資産を手渡しておきたいが、遺産分割で戻されると困る場面。
- 他の相続人との合意が得やすい環境にある家庭。信頼関係があり、持ち戻し免除の条件を文書にまとめられる場合。
使わないほうが良いケース
- 相続人間で関係がぎくしゃくしている、または揉めやすいと予想されるケース。後で「不公平」をめぐる争いが起こるリスクがある。
- 遺留分を考慮しなければならない相続人がいる場合、その人の遺留分の取り扱いが影響を受けることがある。
- 財産の価値が将来大きく変動する不動産や市場価値が不透明な資産が多い場合。将来の評価が上がるかもしれない土地を早く贈与して持ち戻し免除をしてしまうと、結果として「高く売れたはずのものを手放した」ことになる可能性もある。
第5章|生前贈与の落とし穴:持ち戻しが不要と思っていたら困ること
いくつか実際に確認された落とし穴があります。
- 口頭での約束のみだったため持ち戻し免除が認められなかった
書類で条項を残していないと、他の相続人との協議で免除を主張できないことがあります。 - 遺言書の記載が不明確
「贈与されたものは持ち戻さない」という表現があいまいで、裁判になるケース。 - 遺留分請求がある場合の請求額の計算
遺留分制度があるため、持ち戻し免除の条項があっても遺留分を請求されれば、それが制限されないことがあります。 - 評価額の変動リスク
贈与したときより後で不動産地価が上がると、「将来もっと価値が上がるはずだったものを早く渡してしまった」という機会費用が生じる可能性。
第6章|制度の使い方:具体的ステップ
持ち戻し免除を活用するには、以下の手順が重要です。
- 財産目録を整理する
不動産、預貯金、保険、その他資産をリストアップ。 - 法定相続人を確認する
配偶者とお子さん二人(あなた含む)の3人など。 - 生前贈与をする場合は契約書を作る
「持ち戻し免除」という条項を明記すること。贈与日、贈与対象、受贈者、免除の旨。 - 遺言書にも免除条項を入れておく
遺言書の中で、過去の贈与について「持ち戻さない」と指示する。 - 税理士など専門家にシミュレーションを依頼する
相続税額の比較、将来の見通し、遺留分リスクなどを試算してもらう。 - 遺産分割協議で合意をとる
相続人全員の理解と同意を得ておくことが、後々のトラブル回避になります。
第7章|事例:持ち戻し免除を活用した相続対策
以下は、架空に近いが現実的なケースモデルです(実際にあったご相談例をもとに改変しています)。
- 被相続人:父(80代)、自宅と複数の都内不動産を所有
- 相続人:配偶者、長女(65歳・あなた)、次女(40歳)
- 生前の贈与:長女に自宅の土地の一部を贈与、また長女と次女に預貯金の一部を贈与していた
- 遺言書:自宅不動産は配偶者に、残りを長女・次女で等分という内容だったが、長女はすでに土地の一部を受け取っていた
このケースでは、遺言書通りに遺産分割をすると、長女が既に受け取った贈与部分を持ち戻される可能性があり、遺産分割協議・相続税の計算が複雑になる見込みでした。
対策として、持ち戻し免除の条項を生前の贈与契約書に設け、遺言書にも明記。これにより、長女は贈与された土地をそのまま保有しつつ、遺産分割でその分が再度計算されず、相続税の負担が軽減されました。遺留分の確認も行い、次女との協議で現金調整を行うことで合意を得ました。
第8章|まとめ:持ち戻し免除は「対策の一つ」
持ち戻し免除は、生前贈与のリスクを低くし、相続時の遺産分割をスムーズにする有力な手段です。ただし万能ではなく、家族構成・財産内容・遺留分の存在などを考慮する必要があります。
結論としては:
- 生前贈与を検討しているなら、必ず契約書・遺言書に持ち戻し免除条項を設ける
- 税理士などとシミュレーションを取りながら対策を進める
- 遺留分や法定相続人の意思を尊重し、家族間の協議を丁寧に行う
これらを踏まえることで、生前贈与の良い面を活かしつつ、遺産分割時のトラブルや「思わぬ税負担」を防ぐことができます。
もし「うちでもこの方法が使えるか知りたい」「契約書や遺言書の書き方を教えてほしい」ということがあれば、ぜひ当センターへご相談ください。専門家として、客観的・制度的な視点でアドバイスさせていただきます。
当センターのご相談ポイント
- 認定相続診断士・税理士・司法書士と連携したトータルサポート
- 初回相談無料・土日夜も対応可能・女性スタッフ在籍で安心
- 納税資金の目安や制度の活用シミュレーションも無料作成
👇 ご予約はこちらからどうぞ ↓